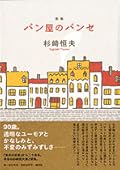 杉崎恒夫第二歌集『パン屋のパンセ』(六花書林)。かつて東京天文台勤務(経理課長)で、且つ、私が大好きな佐藤弓生氏と同じ「かばんの会」の歌人と知り購入。残念なのは、本書出版前に急逝されていたこと。私が最初に「かばんの会」に関心を持った頃は元気に活動されていた筈で、存命中に存在を知りたかった。
杉崎恒夫第二歌集『パン屋のパンセ』(六花書林)。かつて東京天文台勤務(経理課長)で、且つ、私が大好きな佐藤弓生氏と同じ「かばんの会」の歌人と知り購入。残念なのは、本書出版前に急逝されていたこと。私が最初に「かばんの会」に関心を持った頃は元気に活動されていた筈で、存命中に存在を知りたかった。まず、好きな歌を十首選んでみる。 ゆで卵匙にうつ時にわとりの水子の霊がぴよとささやく 不実なる手紙いれてもわが街のポストは指を噛んだりしない 透明なたましいをひとつ住まわせる砂時計この空っぽの部屋 星空がとてもきれいでぼくたちの残り少ない時間のボンベ わたくしが鳥となるとき夕焼けの硝子とびらはつぎつぎ開く 晴れ上がる銀河宇宙のさびしさはたましいを掛けておく釘がない 高原の風に揺れゆれ誰よりもしあわせなのはコスモス自身 食うものと食われるものの関係を焼き魚(うお)の目はだまってみている にんげんは爆発しないで死んでいく星間物質(ダークマター)になれない理由 冬空に神さまがいてもいなくても飛行機雲は意思を貫く 厳密には、星間物質(intersteller matter; ISM)のうち光学的には観測できない分が暗黒物質(dark matter)であって、星間物質(ダークマター)とルビを振るのは不正確と思うが。“暗黒”ではなく“星間”であることが必要なら、読みは星間物質(アイエスエム)? ……他人に意味が通じないな(汗)。
〈銀河宇宙〉〈星間物質〉などは言葉自体が派手なので、経歴と相まって、宇宙関係の歌が多いイメージを持ち易いが、実際は、虫や植物や、身の回りにある物の歌が主流だと思う。第一歌集(未読)が『食卓の音楽』で本書が『パン屋のパンセ』、食べることが好きなのではないか。
「~な歌が多いな」と思うときは大抵、自分はそういう歌を詠まないということで。確かに、私は飲食物の歌は少ない。 あり余る時間あるなり少年のブーメラン夕陽をめぐりて還れ この歌と上記十首中の「星空が」は、私の中でセットになっている。本書に収録されているのは著者が〈70代から80代に創作した歌〉だからか、自分の人生の残り時間を明確に意識して詠んでいる、と感じる。佐藤氏の第三歌集『薄い街』も全体に死の気配が漂う本だったが、“死”の現れ方が違うんだよね。違いは上手く説明できないけれど。 ところで本書、否定で終わる歌が多いと思う。語調が強いから印象に残るだけで、正確に数えれば比率はそんなに高くないのかもしれないが。 さみしくて見にきたひとの気持ちなど海はしつこく尋ねはしない 砂時計の砂にえくぼの浮くときもすぐ倖せは信じはしない 「大切なものは見えない」友達にしたいキツネは街にはいない 思いっきりクレーンが手を延べるとき都会の夜に神さまはいない 私がこれまで熟読した歌集は、佐藤氏の3冊のみ。「~な歌が多いな」と思うときは、自分の歌以外に、佐藤氏も基準としているのでは、と気付いた。確認しないと断言できないけれど、佐藤氏は否定で終わる歌が少ないのかも。 それならば俺はどうなのだ詩人とは少年のままに老いてゆく人 詩人には少年少女の心が必要。でも、小説を書くためには大人の視点が必要だ、と個人的には思った。 PR |
|
|



