 娘が誕生日プレゼントを買ってくれるというので、書店で萩原慎一郎『歌集 滑走路』を選んだ。特に予備知識はなかったが、文庫になってる短歌集は珍しいので。 娘が誕生日プレゼントを買ってくれるというので、書店で萩原慎一郎『歌集 滑走路』を選んだ。特に予備知識はなかったが、文庫になってる短歌集は珍しいので。目次を見て、妙に見出しが多いな? と思い、通読して理解。この歌集、五首とか七首とかの連でタイトルついてるのが多いんだ。 ……詠む側の立場としては、長い連で統一感出すの大変なんだけど。 読む側としては、十首かそれ以上ある長いのが好きなんだな私、と気付く。連の変わり目で気分が切れるのよね……。 歌集の感想恒例、好きな歌を十首選んでみる。 挫折などしたくはないが挫折することはしばしば 東京をゆく 青空の下でミネラルウォーターの箱をひたすら積み上げている 風景画抱えて眠るように ああ あの青空を忘れたくない クロールのように未来へ手を伸ばせ闇が僕らを追い越す前に 空だって泣きたいときもあるだろう葡萄のような大粒の雨 至福とは特に悩みのない日々のことかもしれず食後のココア 遠くからみてもあなたとわかるのはあなたがあなたしかいないから サンタクロースあなたにぼくは逢いたくて逢えず大人になってしまった デモ隊の列途切れるな 途切れないことでやがては川になるのだ 叩け、叩け、吾がキーボード。放り出せ、悲しみ全部。放り出せ、歌。 PR |
 昨夜が、普段の満月より大きく見えるスーパームーンだったので「月百首」を読み返したくなり、佐藤弓生さんの第四歌集『モーヴ色のあめふる』を久しぶりに開いた。mauve(仏語)とは、薄く灰色がかった紫色だそうだ。 昨夜が、普段の満月より大きく見えるスーパームーンだったので「月百首」を読み返したくなり、佐藤弓生さんの第四歌集『モーヴ色のあめふる』を久しぶりに開いた。mauve(仏語)とは、薄く灰色がかった紫色だそうだ。まだ選んでいなかった、恒例の好きな歌を十首を選んでみる。 けんかした みずうみふかくしまわれて忘れたことを忘れた小石 雲が……。ねえ縁側に来ておすわりよ、落ちてゆくのはいつでもできる ふれたならそれはみな星 こえ こころ ことばはやがて腐敗する星 人は血で 本はインクで汚したらわたしのものになってくれますか ふる雨にこころ打たるるよろこびを知らぬみずうみ皮膚をもたねば (スヰングバイ)(スヰングバイ)と水夫のこゑ (さらば金星)(さらば人生) 人はすぐいなくなるから 話してよ 見たことのない海のはなしを ひとの恋ひとの死いくつ映せども空の鏡は忘れる鏡 言語野はいかなる原野 まなうらのしずくを月、と誰かがよんだ 月は死の栓だったのだ抜かれたらもういくらでも歌がうたえる この歌集の印象を三語で表すと、「死」「忘却」「ことば」かな。著者あとがきに〈人がすぐ死ぬこの世をうたいながら〉とあるように、本書に限らず佐藤さんの歌は死のイメージが強いのだけれど。 |
 先日、藤木直子訳『エミリ・ブロンテ全詩集』(大阪教育図書)を買ったあとで知ったが、他に中岡洋訳『エミリ・ジェイン・ブロンテ全詩集』(国文社)というのも出ている。 先日、藤木直子訳『エミリ・ブロンテ全詩集』(大阪教育図書)を買ったあとで知ったが、他に中岡洋訳『エミリ・ジェイン・ブロンテ全詩集』(国文社)というのも出ている。国文社版の「番外 詩連(しばしば叱られても いつも戻ってくるのは)」という詩、詩連という言葉は大阪教育図書版でのスタンザらしいが、該当する詩が載っていない気がする。あと、国文社版にはゴンダル物語の粗筋が載っているらしい。 その番外の詩は、ネットで見つけたので、メモっておく。 |
 藤木直子訳『エミリ・ブロンテ全詩集』(大阪教育図書)を買った。 藤木直子訳『エミリ・ブロンテ全詩集』(大阪教育図書)を買った。私、1988年頃に古本で買った文庫の『嵐が丘』の解説で、エミリが妹アンと作り上げた「ゴンダル物語」に属する詩の一部を読んだことがある。そのときの記憶と、本書での訳が大分異なる気がして、調べてみた。 実家の『嵐が丘』の出版社・訳者は覚えていないが、リントン邸を〈スラシクロス・グレンジ〉と表記していたことから、角川文庫の大和資雄訳と思われる。大和資雄訳のゴンダル詩をネットで検索すると、何となく見覚えのある下記の詩が見つかった。 |
 第二歌集『パン屋のパンセ』(感想)が良かったので、杉崎恒夫第一歌集『食卓の音楽』(六花書林)も買ってみた。『パン屋』では「否定で終わる歌が多い」と思ったが、本書は否定形少ないね。 第二歌集『パン屋のパンセ』(感想)が良かったので、杉崎恒夫第一歌集『食卓の音楽』(六花書林)も買ってみた。『パン屋』では「否定で終わる歌が多い」と思ったが、本書は否定形少ないね。まず、好きな歌を十首選んでみる。 ひしめきて壺に挿される薔薇たちの自分以外の刺を痛がる されど欝されど倖せコーヒーの底にみえないものを飲み干す 「信じるのはやめてください」温室に冬汗ばみて読む花ことば こんなにも明るい秋の飛行船ひとつぶの死が遠ざかりゆく 一枚の影絵となってしまうまで冬の欅と鳥の関係 火に落ちしドン・ジョヴァンニの叫喚が雨の歩道のうしろより来る 夏蝉も終りて候う月の国静かの海へあてたる手紙 毒のないぼくの短歌とよくなじむ信仰心のうすいマシュマロ 陽は遠く秋分点を超ゆる日のかたみのごとく曼珠沙華咲く 銀杏の青き実落つる風の朝 石女の詩をひとつ愛せり 歌人はクラシック音楽がとても好きなのだろう、音楽家や曲名や楽器の名前が歌に頻出する。しかし、私に素養がないために解らん(汗)。ドン・ジョヴァンニだけは、映画『アマデウス』を観たので解る。 で、私が好きな歌を選ぶと、私でも解る植物や自然の歌が多く残る模様。 |
 『世界が海におおわれるまで』(感想)『眼鏡屋は夕ぐれのため』(感想)に続く佐藤弓生第三歌集『薄い街』(沖積舎)。先日、杉崎恒夫『パン屋のパンセ』(感想)を購入した際に読み返して、好きな歌十首をまだ選んでいなかったことに気付き、選んでみた。
『世界が海におおわれるまで』(感想)『眼鏡屋は夕ぐれのため』(感想)に続く佐藤弓生第三歌集『薄い街』(沖積舎)。先日、杉崎恒夫『パン屋のパンセ』(感想)を購入した際に読み返して、好きな歌十首をまだ選んでいなかったことに気付き、選んでみた。あり過ぎて十首に絞るのが難しいが、あえて絞ることで、自分の好みの優先順位が見えてくる。 まてんろう 海をわたってわたしたち殖えていくのよ胞子みたいに 悲しいというのはいいね、濡れながら、傘を買わなくてもかまわない (愛されるために生まれた)(そうだった)洗濯槽にまわる泡たち 白かった猫の話にたれか泣く 泣くことは歌うことだったから もうみんなとおくへ行ってしまったよ死のことばかり考えていて とざすべきまぶたいちまいもたぬ空 ころされるのはこわいだろうか かるい紙きれいな紙を折りましょう折り目を二度と消せないのなら 飛ぶ紙のように鳥たちわたしたちわすれつづけることが復讐 朝露のこわれるまでをくるしみは嘘がつけないから見ていたい この人といつか別れる そらみみはいつも子どもの声をしている 昨年の初読時は「飛ぶ紙の」が一番好きだったが、今は「もうみんな」が好きだ。読む時によって、選ぶ十首が変わるかもしれない。今回は“ひらがな表記が印象的な歌”が残った気がする。 |
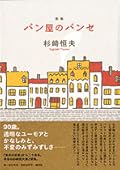 杉崎恒夫第二歌集『パン屋のパンセ』(六花書林)。かつて東京天文台勤務(経理課長)で、且つ、私が大好きな佐藤弓生氏と同じ「かばんの会」の歌人と知り購入。残念なのは、本書出版前に急逝されていたこと。私が最初に「かばんの会」に関心を持った頃は元気に活動されていた筈で、存命中に存在を知りたかった。
杉崎恒夫第二歌集『パン屋のパンセ』(六花書林)。かつて東京天文台勤務(経理課長)で、且つ、私が大好きな佐藤弓生氏と同じ「かばんの会」の歌人と知り購入。残念なのは、本書出版前に急逝されていたこと。私が最初に「かばんの会」に関心を持った頃は元気に活動されていた筈で、存命中に存在を知りたかった。まず、好きな歌を十首選んでみる。 ゆで卵匙にうつ時にわとりの水子の霊がぴよとささやく 不実なる手紙いれてもわが街のポストは指を噛んだりしない 透明なたましいをひとつ住まわせる砂時計この空っぽの部屋 星空がとてもきれいでぼくたちの残り少ない時間のボンベ わたくしが鳥となるとき夕焼けの硝子とびらはつぎつぎ開く 晴れ上がる銀河宇宙のさびしさはたましいを掛けておく釘がない 高原の風に揺れゆれ誰よりもしあわせなのはコスモス自身 食うものと食われるものの関係を焼き魚(うお)の目はだまってみている にんげんは爆発しないで死んでいく星間物質(ダークマター)になれない理由 冬空に神さまがいてもいなくても飛行機雲は意思を貫く 厳密には、星間物質(intersteller matter; ISM)のうち光学的には観測できない分が暗黒物質(dark matter)であって、星間物質(ダークマター)とルビを振るのは不正確と思うが。“暗黒”ではなく“星間”であることが必要なら、読みは星間物質(アイエスエム)? ……他人に意味が通じないな(汗)。 |
 今日中にしなくてもいいことばかり片づいていく締め切り前夜
今日中にしなくてもいいことばかり片づいていく締め切り前夜立ち読みでこの歌を気に入り、佐藤真由美第一歌集『プライベート』(集英社文庫)を買った。 ……しかし。「面白い歌が多い」とは思うが、気に入った歌が、上記1首しかない(汗)。というわけで、“面白い歌”を5首挙げてみる。 |
 加藤千恵『ハッピーアイスクリーム』(中公文庫)。文庫で手に入る短歌の本、ということで書店で探していたが、なかなか見つからない(汗)。買うと決めた本ならネット注文するが、中を見ないと気に入るかわからないからねぇ。
加藤千恵『ハッピーアイスクリーム』(中公文庫)。文庫で手に入る短歌の本、ということで書店で探していたが、なかなか見つからない(汗)。買うと決めた本ならネット注文するが、中を見ないと気に入るかわからないからねぇ。で、神保町の三省堂でやっと発見。……えーと、短歌はいいと思うんだ、短歌は。装丁! 外も中も、ピンク過ぎ(汗)。好みの問題だろうが、個人的には「大人しく短歌だけ読ませて」という気分である。 |
 先日宣言したとおり、佐藤弓生『世界が海におおわれるまで』(沖積舎)から、好きな歌を十首挙げてみた。
先日宣言したとおり、佐藤弓生『世界が海におおわれるまで』(沖積舎)から、好きな歌を十首挙げてみた。満ちてくるほのおのにおい放課後は実験室の春のはじまり てのひらに卵をうけたところからひずみはじめる星の重力 夕焼けのわけなど問うな今もまだきみは無人の校舎にいるのだ 風鈴を鳴らしつづける風鈴屋世界が海におおわれるまで 神さまの話はとおい海のようビルのあわいにひらく碧眼 子どもたちみな魔女になれ三月の豆腐屋さんのおとうふうふふ 「死後なんかないのよだからねんねして」夜会に向かう母うつくしく 海へゆく日を待ちわびた少女期を思えば海はいまでもとおい 絵空事だけが恋しい かんむりを切りぬきましょう金紙銀紙 ロケットのかがやくあしたあのひとはひとりで泣いてわすれるのだろう 『眼鏡屋は夕ぐれのため』(感想)の際も実感したが、やっぱり私は口語が好きである。 また、『世界』には「擬音語が含まれた歌が多い」という印象があったのだが、上位十首にはあまり残らないんだよなー。かろうじて、「うふふ」が擬音語かな。 |
 佐藤弓生氏の第二歌集、『眼鏡屋は夕ぐれのため』(角川書店)。処女歌集『世界が海におおわれるまで』(感想)と比べると擬音語が減った、というのが第一印象。そして、どう言えば適切な表現なのかが分からないが、「……物騒になったなぁ」(汗)。
佐藤弓生氏の第二歌集、『眼鏡屋は夕ぐれのため』(角川書店)。処女歌集『世界が海におおわれるまで』(感想)と比べると擬音語が減った、というのが第一印象。そして、どう言えば適切な表現なのかが分からないが、「……物騒になったなぁ」(汗)。語り始めると止まらないので、とりあえず好きな歌を十首挙げる。なお、“物騒”な歌は、意図的に外したわけではないが、この中にはない。上位十首に入らなかったんだよねぇ。 もう西がどちらかわからなくなってつめたい海が 海がはじまる さみどりの庭 これまでの夏はなくこれからの夏もないとばかりに 青空が折りたたまれてあるまひる曲がり角とはいたましい場所 かんたんなものでありたい 朽ちるとき首がかたんとはずれるような 風を聞く 踵をなくしてしまうまで帰るところが海と知るまで 敷石のあいだあいだのハルジョオンなにかがもっとよくなるように 神様とわたしどんどん遠ざかる夜ごと赤方偏移のしらべ 誰の死も願ったことのないようなまぼろしですねこの晴天は にっぽんはうつくしい国あらかじめうしなわれたるうつくしい国 怪獣を空に飼ってた 熱帯夜 わたしたちもう転生しない 並べてみてよく解ったが、私は実に口語が好きだ。佐藤氏は文語表現もよく使う(例:なにひとつわたしのものでないゆえにかろき惑星儀をあがないぬ)のに、見事に一首も選んでいないぞ。 自己満足だが非常に面白かったので、今度『世界』からも十首選んでみよう、うん。 |
 三好達治/著・桑原武夫/選・大槻鉄男/選『三好達治詩集』(岩波文庫)。北村薫『六の宮の姫君』(感想)中で『春の岬』という詩が引用されていたので借りてみたが、作者を知らずに詩だけ知っていた作品が、結構あるなあ。『Enfance finie』という作品中の「空には階段があるね。」というフレーズは確か、森博嗣『封印再度』に出てきたような。他にも、
三好達治/著・桑原武夫/選・大槻鉄男/選『三好達治詩集』(岩波文庫)。北村薫『六の宮の姫君』(感想)中で『春の岬』という詩が引用されていたので借りてみたが、作者を知らずに詩だけ知っていた作品が、結構あるなあ。『Enfance finie』という作品中の「空には階段があるね。」というフレーズは確か、森博嗣『封印再度』に出てきたような。他にも、太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ 次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。 『雪』 海よ、僕らの使ふ文字では、お前の中に母がゐる。 そして母よ、仏蘭西人の言葉では、あなたの中に海がある。 『郷愁』(部分) 蟻が 蝶の羽をひいて行く ああ ヨットのやうだ 『土』 個人的には、『鴉』が気に入った。〈私〉が突然、鴉になって飛んでいく詩。 |
|
向井ちはる『OVER DRIVE』(フーコー)。
彼方からトランポリンにすべり落ち突き抜けるほどジャンプしなくちゃ 第2回フーコー短歌賞大賞を受賞して出版された、この歌集。このところ口語短歌に関心があった私は、賞を主催した新風舎のホームページに載っていた選考委員による選評を読んだのですが。 疾走感。スピード。ハイテンション。 そんな表現で絶賛されていたこの『OVER DRIVE』に興味を持ち、買ってみたのです。 |
|
| ホーム |
|




